いよいよ節分!!冬と春の区切り?
そうですが、この方角を
図に書くと丁度鬼門の方向になるところです!!
併せて太陽の年取?
ここで悪い鬼が入ってこない様に・・・と
豆まきをして
邪気を払う!!
こんなイメージではないでしょうか?
岩手の地区では、大豆に替えて
落花生ですね
本日、この落花生・・・
大量入荷!!してきます。
価格?・・・ご来店いただいたお客様にだけ・・・
お知らせいたします!!
 |
日々発見したことや面白いことなどをメモしたものを記録しているものです。 手書きメモや手描きメモ・写真で記録しておきます。コメントについては、すべてにお答えする事ができませんので、ご了承くださいません。すみません・・。 画像は個人でのご利用頂いて結構ですが・・。中・大手流通業者さんの、商用利用の方は基本的にお断りいたしております。使用目的を確認した公共の印刷物、小規模の小売業者さん、鮮魚小売店・個人で経営されている料理店さんには、予めmtmの確認・承諾の上で利用をされている方もいらっしゃいます。 確認はコメントで登録または、メールアドレスはinfo(AT)dnjmb.co.jp ←ATを@に変えてご利用ください。お手数かけますがよろしくお願いいたします。
今週からいよいよスタート!!
本来であれば、昨日から・・・という事なんですが・・
地方の市場はどうしても物が揃わず・・
止むをえず、第二週目という事で・・
じゃんまる津志田店は本日から・・
土日ジャンボ市は11日から
スタートさせていただきます。
どうぞ本年も宜しくお願いいたします。
という事で、久々に長く休める筈でしたが・・・
昨年12月25から31日までの間に・・
PayPayさんの販売データのメールが
一部欠落するという状況が発生し・・・
正月から年間の取引件数・・
十数万件のデータの付け合わせをするはめに・・・(T-T)
その意味で、ゆっくりとプログラムを作れた?・・・お正月でした(笑)
おかげさまで、データは無事復旧いたしました。・・
ということで
本年も宜しくお願いいたします。m(_ _)m
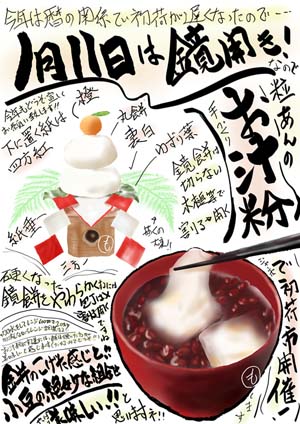 |
アップが遅くなってしまいましたが・・七夕が・・
いよいよ 五節句の一つ七夕がやってまいりますね。
今年は草刈りをしていて、ブヨに刺され・・目が腫れ、目が見えなくなってしまい アップが遅くなってしまい m(_ _)m
五節句は
1月7日 人日(じんじつ)の節句(七草の節句)
3月3日 上巳(じょうし・じょうみ)の節句(桃の節句)
5月5日 端午(たんご)の節句(菖蒲の節句)
7月7日 七夕(しちせき)の節句(星祭り)
9月9日 重陽(ちょうよう)の節句(菊の節句)
あれ?
1月1日の元旦も本来は節句に含まれるべきでは?
と思いますが、1月1日は、別格とされています。代わりに、1月7日が節句として取り入れられています。
中国では奇数は陽の数とされており、縁起の良い数字が重なることで逆に不吉な日とされ、もともとは厄払いする日として捉えられていた模様。
その習わしが変化し、無病息災や子どもの成長などを願って祝い事をする日になった。
昔は五節句の他にも、さまざまな節句があった。しかし江戸時代に、幕府が以下の5つの節句を公的行事の日と定めたことで、これらの節句が行事として残ることになった様です。
太陰暦では太陽暦の8月上旬から下旬にあたる、太陰暦の7月7日に行事が行われていた。 太陰暦の七夕は「伝統的七夕」と呼ばれたりして区別をしているようです。
七夕の行事食
七夕は索餅(さくべい)と素麺(そうめん)が行事食です。
索餅とは、米粉や小麦粉を練ったものをひねって揚げた、中国由来のお菓子のようです。
縄のような見た目から、麦縄(むぎなわ)とも呼ばれます。
中国では、無病息災を祈願して7月7日に索餅を食べる習慣があり、それが日本にも伝わりました。
やがて、時代とともに索餅は同じ小麦粉から作られる素麺へと変化し、現在も風習として残っています。
また、健康祈願や無病息災だけでなく、「天の川に見立てた」「織姫にあやかり、素麺を糸に見立てた」など、
素麺を食べるようになった由来はいくつか説があります。
五色の短冊
七夕に飾られる五色の短冊は、中国の陰陽五行説が起因。
世の中が陰と陽で成り立っているとするこの考え方では、短冊に使われる色に以下の意味を持たせています。
青や緑の短冊:自然をあらわす「木」・(陽)
赤の短冊:炎を表現する「火」(陽)
黄の短冊:大地の象徴である「土」・(中)
白の短冊:大地に埋まる金属を示す「金」・(陰)
黒や紫の短冊:命の育みを示す「水」・(陰)
また、短冊の色には、中国の思想家・孔子が礎を築いた五徳の意味もあります。
青や緑の短冊:人を思いやる心の「仁」
赤の短冊: 仁を具体化した感謝の「礼」
黄の短冊: 誠実さや約束を守ることの「信」
白の短冊: 私利私欲にとらわれない「義」
黒や紫の短冊: 学業に励み向上を目指す「智」
こんな願いが七夕飾りにあるんですね。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
食べものなので好みあると思いますが。久しぶりに「豆腐」を食った感じです! 大豆の…
アメリカ在住して10年経ちます。近所のアジア系スーパーになんと地元岐阜を思い出さ…
はじめまして。私柿澤と申します。 盛岡出身で現在東京でデザイン会社で働いている者…
魚甚 山崎 克己 さま -あらま!!- 了解しました(笑) 私のブログは、単に価…
"#手作り味噌#土日ジャンボ市#社長の手描きメモ #" "くろまめ クロマメ クロヒラマメ くろひらまめ なんぶがんくいくろひらまめ" "なんばん ナンバン 味噌 とうがらし トウガラシ" "アシグロナメコ ナメタケ" "キャンベル ナイアガラ きゃんべる" "ツブ つぶ" "小泉武夫 日本の食事 根菜 葉菜 果物 豆類 魚 海草 お米" "岩手107号 岩手118号" #ひっつみ #もち美人 #モチコメ #土日ジャンボ市 あらん おろし お供え お汁粉 こだわりの箸 しだれ食品,寄せ豆腐,岩泉 ないあがら ないやがら ぶどう もち イチョウ カボチャ ギンナン シナノキ ハローウィン マスカットノワール マダ 串カツ 南瓜 味噌 大豆 平安 白 県産 豆腐 銀杏 鏡餅 青南蛮 青唐辛子 食の安全 餅 鬼 麦
チラシを見て社長さんに声をかけさせていただきました。試して見てーと話題のお豆腐を…