お米について
2003/02/05--motohiro--
ジャポニカ米、粘りがあって日本人が好む。
インディカ米、パサパサで、
インディカ種とジャポニカ種のちがいは、ひと言で言うと「インディカ種は細長くてねばりの少ない米、ジャポニカ種はずんぐりしていて粘りの強い米」ということになります。これは、お米の主成分はでん粉という炭水化物なのですが、これを構成しているアミロースという糖分の種類のちがいによります。日本ではほぼ 100パーセントがジャポニカ種のお米ですが、日本をのぞくほかのアジア諸国ではインディカ種が圧倒的に主流なのです。
はじめ、ジャポニカと同時期にインディカも日本に伝来しましたが、日本人はジャポニカを好みました。お米には味付けをせず、炊いてそのまま食べるようになりました。そのため、おかずとご飯を分ける食文化が生まれたのです。一方、インディカを食べている地域では、舌触りがパサパサしているためか、そのまま食べず、カレーと合わせたり、炒めたりと味付けをして食べることが多いようです。長い歴史のなかで、その土地の気候風土にあったお米が作られるようになり、また、そのお米の特徴にあった食べ方がされてきたのです。
お米の家系図
玄米は薄い種皮で覆われています。精米することによって種皮と胚芽を合わせた(糠)と、白米(胚乳)にわかれます。
| 玄米 |  |
胚芽精米 | 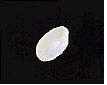 |
| コシヒカリ精米 | 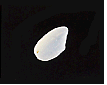 |
無洗米 | 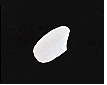 |
種皮・胚芽・胚乳の割合はおよそ 6:2:92です。 栄養価が高くいろいろ体に良い効能がありますが食べにくいと言う欠点もあります。その点、白米は胚乳(でんぷん)以外を取り除いてしまうので、食味は大変良くなります。 ■五分精米とは 糠と胚芽の合計量に対しその半量を除去した米 ■七分精米とは 糠と胚芽の合計量に対しその7割を除去した米
|
|||
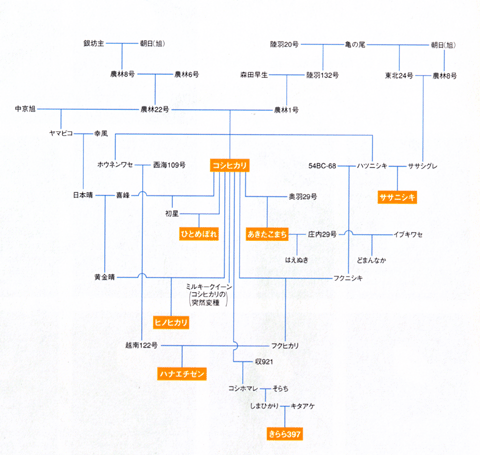
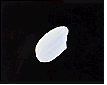
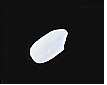
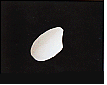
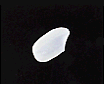
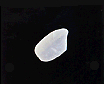
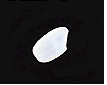
おにぎり コシヒカリ・ひとめぼれ あきたこまち
寿司 ササニシキ・ハナエチゼン・ハツシモ・あきたこまち
日本晴+コシヒカリ
チャーハン・ピラフ キララ397・日本晴・ほしのゆめ
丼 はえぬき・ハナエチゼン・ササニシキ・キヌヒカリ
炊きこみご飯 夢ごこち・ミルキークイーン+コシヒカリ・コシヒカリ・
ひとめぼれ
お弁当
(冷めても美味しい) あきたこまち・夢ごこち・ミルキークイーン+コシヒカリ
◆無洗米は、最近急激に普及し身近なものになってきております。
最新の統計によると、現在無洗米の市場は、年間1555億円とも言われ、昨年(平成13年)一年間でも、1.5倍の普及率です。認知率も70%を超え、また全国では、無洗米専門店も現れたり、一部家電メーカーでは、電気炊飯器の水加減の目盛りに無洗米の目盛りを設けるなど、今後更に普及することが考えられます。そこで、無洗米について本当のところどうなのかどうか、考えてみたいと思います。
まず、無洗米とは?
社団法人日本精米工業会は無洗米の定義を次のようにしております。
「無洗化処理精米(無洗米)とは、普通の米を専用の無洗化処理装置により処理し、炊飯の際、水洗を必要としない程度に精製された精米を言う」としています。また、無洗米協会のホームページhttp://www.musenmai.com/を見ると更に次のように書かれております。
安全面
異物をきれいに除去する異物除去機が整っていること
清潔な米に仕上がっていること(耐熱性細菌数が最低測定基準の300/g以下)
加工時に空気・水以外は使用していないこと
清潔な工程で生産されていること
品質面
研がずに炊けるほどヌカがキッチリ取りきれていること
(濁度測定では35ppm以下)
米肌を傷めず無洗米加工されていること(米粒表面の拡大観察)
無洗米加工しても食味が落ちないこと(うまみ層の残留検査)
環境面
無洗米工場からとぎ汁や汚水・汚泥が出ないこと
無洗米加工時に除去されたヌカは、有効利用されていること
ゼロエミッションであること
省エネルギーで生産されていること
(無洗米1kg加工に要するエネルギーがCO2換算で6g以下)
では、無洗米はどのようにして作られるのでしょうか。
無洗米加工には大きく分けて、3種類の加工方法があります。
「特殊加工仕上げ方式」
これは、精米された白米の表面に付着している肌ヌカを、特殊な技術で除去する方法です。メーカーによって手法は異なりますが、同じ肌ヌカで除去する方法(BG無洗米)、タピオカでんぷん粉を使って除去する方法(TWR無洗米)があります。
(TWR無洗米は、次の湿式法の加工方法に入れる考え方もありますが、ここでは、水以外の物に肌ヌカを付着させて加工する観点から特殊加工仕上げ方式とします。)
「加水精米仕上げ方式、湿式法」
これは、水流により、短時間でヌカを取り、脱水、乾燥させる方法。
「乾式研米仕上げ方式」
これは、水を一切使わず、研米機などで肌ヌカを除去します。
炊飯する時に、軽く1〜2回洗米したほうがいいみたいです。
なお、各メーカーとも、一切の化学薬品は使用しておりません。
次に、無洗米が一番注目されている、環境面で、無洗米の効果はどうでしょう。
そのような観点で、最近、ISO取得の企業などが、社員食堂でとぎ汁の出ない無洗米を積極的に採用しております。
さて、最後に、無洗米はおいしいか、栄養価はどうか、と言う問題です。
無洗米が、始めて市場に出たときは、食味の悪い点は、各無洗米製造機械メーカーも認めておりましたが、最近では随分改善されてきました。
一番多い、クレームの一つは、水加減の問題ですが、大体、各メーカーとも、米との重量比が米1対水1.5〜1.65の割合であると、問題がないようですね。
(各メーカーによって、水加減が若干変わってくる)
各メーカーのホームページを見ていると、食味試験データーを載せておりますが、条件が完全に一致しておりませんので、あくまでも参考資料として見たほうがいいです。
それと、表面に残存している細菌の数をPRしているメーカーもありましたが、これは、余り問題にする事はないようです。個人的には糠くさいと感じますので、やはり軽く糠をとった方がいい。
さて、栄養価の問題ですが、これは、加工の仕方、普通精米ですと、研ぎ方にもよりますので、一概に言えません。
多様化米について
通常のお米のほかに、ある特定の特徴を品種改良により、強めたお米です
低コスト米 多収・耐病性・機械化適応性などを前提に品種改良されたお米
低アミロース米 うるち米ともち米の中間に位置する「半もちタイプ」で、玄米の大半は白濁しているものが多い。
粘り強く炊き上がりも艶はありますので、食べた感じでは今はやりの食味嗜好に合うと思えるお米。一般にはブレンド用として用いる。
品種としては、彩・ねばり勝ち・ミルキークイーン・夢ごこち・スノーパール・はやぶさ等がある
高アミロース米 低アミロース米の逆である。であるから、粘りがない米である。通常アミロース含有量が、27%〜30%位の品種を言う。
ピラフ、チャーハン、リゾット、冷凍米飯等に適する。
品種としては、夢十色、ホシニシキ、ホシユタカ
紫黒米 一般には、黒米と言われる、古代米。うるち米の黒米、もち米の黒米がある。
鉄分、カルシューム、各種ビタミンを多く含み、また、炊きあがりの色も楽しめて、最近人気となっている。
品種としては、紫雲、おくのむらさき、朝紫、紫宝など
赤米 黒米同様、古代米である。赤飯のルーツとも言われ、神事に用いられる。
黒米と比べると、不味い。
品種としては、ベニロマン、紅更紗、紅香
低アレルゲン米 通常品種に比べ、易消化性タンパク質のグリテリン等を抑えたお米である。
タンパク質摂取制限が必要な、腎臓疾患患者の病態食に向く。
品種としては、LGC−1、春陽
巨大胚芽米 通常米の3〜4倍の重量の胚芽を持つ米。健康食品用に向く。
品種は、はいみのり。
香り米 通常の炊飯に、少量混ぜると、良い香りがする事から、香り米という。
最近特に開発が進む。
品種は、キタカオリ、はぎのかおり、プリンセスサリー、さわかおり、かほるこ、などがある。
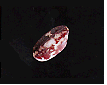
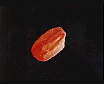
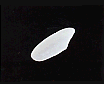
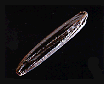
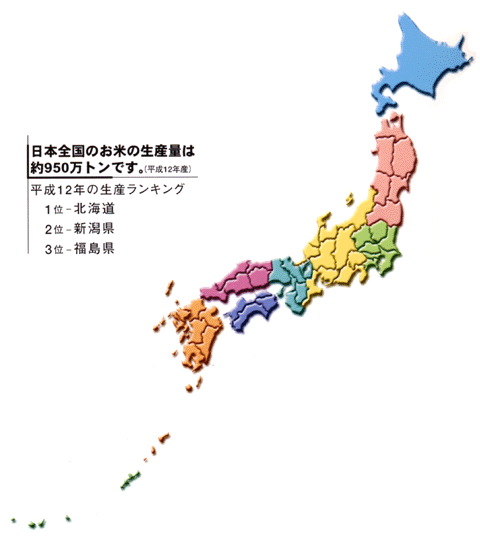

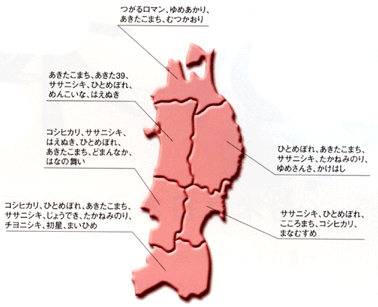
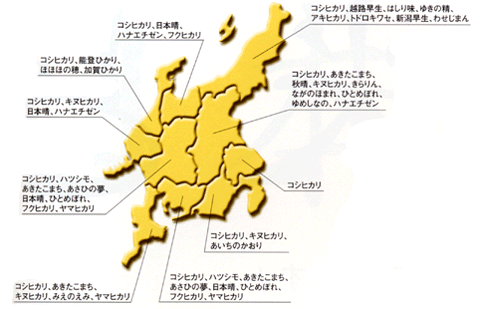
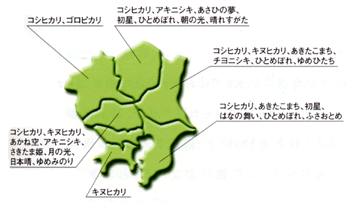
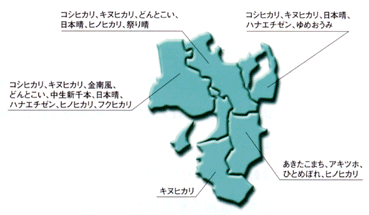
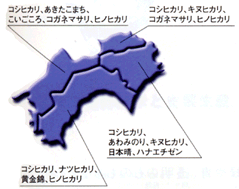
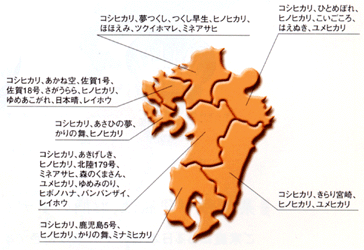

通常の米作りの場合、窒素分解換算で10kg前後の化学肥料が必要だが、EM菌を使用すると窒素分2kg、肥沃な土壌であれば無肥料で栽培できる
アルギットには、ミネラル、アルギン酸、ビタミン等の栄養分を豊富に含んでおり、稲だけでなく、土壌内の微生物にも栄養を与え、良質の土壌を作ることが出来る
活性炭 つまり、炭を土壌に埋設すると、空気や水をシッカリ含み、微生物の住み家として最適な環境を作り上げる
その上、土壌に多い腐性菌やカビ等は入り込めず、有効微生物の住み家となって土壌生態系のバランスを作物にとって良い方向に変えてくれるため、安全な土壌改良材や浄化材として炭が見直されている 。
農業分野以外で使われることが多かったが、現在は農薬の代わりにも使用されている
通常500〜1000倍に希釈し散布すると、作物の生理代謝を促し、病害虫に強くなり、アミノ酸の生成を強めて食味を良くする
また、土に施すと土壌病害を減らし有効微生物の生育を助けたり、堆肥作りでは発酵が良く進む等の効果もある
ただ、木酢液の成分は200種類以上もあり、何故そのような効果があるのかは良く解っていない
雑草や害虫を食べてくれるので、農薬を使わなくても、除草や害虫駆除が出来る。合鴨を圃場に放つもう一つの効果は、合鴨が泳ぐ事で土をかくはんする事で、酸素が土に混ざり、根から酸素が吸収される。さらに、合鴨のフンも肥料になる
ただ、合鴨を育てる手間や、烏やキツネ等の天敵から合鴨を守る労力もいる。
合鴨の場合は、稲が合鴨に食べられない丈になるまで圃場に入れられないが、コイは田植え後すぐに入れることが出来るので、早期から除草の効果が期待できる
天然石こうを主原料とするカルシウム肥料を使った農法
この肥料を使用すると、稲の栄養成長期にカルシウムを充分に吸収するので、茎葉がシッカリとして、生育が良くなるという
緑健農法 原産地に学び、土を耕さず、水も肥料も極力控えて中身の濃い(高ミネラル、高ビタミン)作物を育てる農法
アビオン農法 パラヒィンや桂皮アルデヒド(ニッキ)など安全性の高い食品添加物を原料とした防除資材(アビオン)を用いた農法
黒砂糖・酢農法 黒砂糖に水を加えてバイエム酵素で発酵させたものをベースにして、作物の種類や生育状況に応じて、酢・焼酎・各種微量要素を加えて随時葉面や果実に散布し、品質収量の向上を図る
クリノゼオライト農法 腐埴と同じ保肥力を保ち、石灰その他の養分をしっかり効かせるクリノゼオライトと、水溶性石灰サンカルシウムの飛躍的な窒素吸収で増収を実現する。
息吹農法 水をたっぷりやるほど土を膨軟にする。これが、息吹の魅力である。わずかな量で土を瞬時に団粒化し、作物は徒長知らずでみずみずしく育つ。
ハイポニカ農法 土を用いず、液肥と空気を混入して循環させた栽培層の養液の中に根を伸ばす。一株のトマトが、巨木に生長し、1万個以上もの実をつける。
酵素農法 植物活性酵素(万田31号)果実、穀類、海藻類など50数種類に及ぶ、原材料を熟成発酵させ、植物の生育に携わってきた物質を引き出したものです。植物が生命力を引き出し、活力を与え、生育を促進する農法。
カルゲン農法 土壌の中に、有機石灰を投入することで、土壌が固くなることを防ぎ、微生物の働きを活発にし植物と共生する農法。
もともと稲の乾燥には「天日干し」しかしなかったが、あまりにも労力と日数がかかるため、今では大型乾燥機が開発され、強制乾燥する方法が主流となった。しかし、乾燥機に入れるとコメの表面が羽毛立ち味が落ちる」とも言われ、自家消費分だけは天日干しにする農家も少なくないという。
「天日干しの美味しさは格別で、銘柄の違いなど問題にならない」とまで言われている
病害虫の防除や除草などの目的で使用された農薬が、作物などに残ること。
農薬取締法では、人の健康や環境に悪い影響を与える農薬の使用は認めておらず、それに基づいて、厚生省や環境庁が各種の基準を設置しています。
作柄の良否を示す指標のことで、通常は10a当たり平年収量に対する10a当たり収量(または調査時ごとの10a当たり予想収量)の比率で表します。
作況指数と作柄良否の関係は、現在、以下の5段階で評価されています。
106以上 良 105〜102 やや良 101〜99 並 98〜95 やや不良 94以下 不良
単位 重さ 容量 メモ
1勺(しゃく) 約15g 0.18ml
1合(ごう) 約150g 180.4ml 1勺の10倍
1升(しょう) 約1.5Kg 1.8039リットル 1合の10倍
1斗(と) 約15Kg 18.039リットル 1升の10倍
1俵(ひょう) 60Kg 72.156リットル 1斗の4倍
1石(こく) 約150Kg 180.36リットル 1斗の10倍
尺貫法の容積の単位です。尺貫法は昭和34年に廃止されました。
私達米屋の場合、流通は30k袋での取引が主ですが、単位は俵で取引する事が多いです。30K袋×2で1俵ということです。
1歩(ぶ) 1坪と同じ。 3.3平方メートル
1畝(せ) 1歩の30倍。 約10m×10m
1反(たん) 1畝の10倍。 約10m×100m
1町(ちょう) 1反の10倍。 約100m×100m
「おいしい!」という感覚はつきつめて言えば人それぞれ。しかも舌で感じるだけでなく、見た目や香りなど五感すべてが関わってきますから、なかなか「これ!」という基準は決めにくいものです。微妙な味わいを楽しむごはんの場合は、なおさらむずかしいのですが、お米の成分の分析によって、ある程度食味の判断をすることができます。なかでもポイントはたんぱく質とでんぷん。たんぱく質の多いお米は一般においしくないとされています。そして、でんぷん。お米にはアミロースとアミロペクチンという2種類の成分がありますが、粘りと硬さのバランスはこの2種類の成分の比率で決まります。
たとえば、もち米はアミロース含有量がゼロです。逆にインディカ米の中にはアミロース含有量が24%以上の高アミロース米もあります。つまり、アミロースが多いほど、お米は硬く、パサパサとしているイメージ。日本人に関して言えば、アミロースが少なめのお米が好まれる傾向があり、おいしいとされるコシヒカリのアミロース含有量は約16%です。なお、アミロース含有量が16%前後のお米は、冷めてもおいしいという特性も持っています。
<ご飯にした場合の栄養価の違い(可食部100g当たり)>
精米の種類 エネルギー量 たんぱく質 カリウム リン ビタミンB1 食物繊維
玄米 165kcal 2.8g 95mg 130mg 0.16mg 1.4g
五分づき米 167kcal 2.7g 43mg 53mg 0.08mg 0.8g
七分づき米 168kcal 2.6g 35mg 44mg 0.06mg 0.5g
胚芽米 167kcal 2.7g 51mg 68mg 0.08mg 0.8g
白米 168kcal 2.5g 29mg 34mg 0.02mg 0.3g
「五訂日本食品標準成分表」より
日本では、主食の米を三つの方法で加熱調理する
焼く→糒(ほしい)
蒸す→強飯(こわい)
煮る→粥(かゆ)
古代の日本人はお米を籾のまま焼いて食べていたことが、遺跡から出土する遺物から推測されます。明治の始めに「焼米食べるべからず」という禁止令が出ていることからも、近年まではポピュラーな食べ方であったことが伺えます。明治の始めには、多分食料事情の問題で、いくらかでも食料を増量して食べるという事もあり、焼き米禁止法ができたのではないかと想像する。香りはとてもいいが、固いので、消化が余りよくないのと、通常食べ続けると、飽きがくる。
調理法
収穫直後の生籾や乾燥した籾殻がついたままのお米を、何の加工もしないで煎って、充分に火を通す。
食べ方
籾を取ってそのまま食べたり、湯茶に浸して食べる。
最初の「強飯」は、木製の甑(こしき)を使って籾を蒸したものでした。
その後、籾を玄米にした後にこれを蒸すなど、食べやすさを増していきます。
さらに少しずつ精白度合いを増していき、白米で「強飯」をつくる形へとたどりつきました。現在では、「強飯」は普通〈もち米〉でつくりますが、古代では〈もち米〉ばかりでなく〈うるち米〉も多く使ったようです。
昔の人は旅行時や戦争時など、どうしても調理器具を持参することができない時に、蒸して乾燥させたお米を携帯食品として持参しました。
食べ方
水に浸してふくらませれば、食べることができました。
固粥→ご飯(我々が通常食べる)
固粥→米と水を1:1〜1:1.25(新米と古米で、量が変わる)
汁粥→固さによって名称が異なる
全粥→米と水を1:5の重量比で炊いた物
七分粥→米と水を1:7
三分粥→米と水を1:15
重湯→米と水を1:10の割合で煮て、汁だけを濾(こ)しとったもの
御交(おまじり)→全粥と重湯を1:9の割合で混ぜたもの
白粥→白米だけでつくったお粥
雑穀粥→稗・粟・黍(きび)・豆などを穀類を入れてつくるお粥
木の実の粥→栗・栃の実・干しぶどう
根菜粥→大根・さつまいも・サトイモ・人参
お粥の味付け
茶粥→お茶で塩味で煮る
甘葛粥→甘葛(あまずら)
七草粥→1月7日の粥 セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコべラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ
小豆粥→1月15日の日
尾花粥→疫病を防ぐためにつくった、ススキや早稲の穂を黒焼にしたもの(代用黒ゴマ)を混ぜて8月1日に食した。
朝粥の風習は西日本
昔は東では、飯は朝に炊いたから粥を食べる習慣はなく、せいぜい病人か小児の食べ物だった
西では、飯は昼に炊いた(昼炊)習いがあり、翌朝はその残りを利用し、利便と経済性を兼ねた名残だという。
「はじめチョロチョロ、なかパッパ・・・」といっても何のことだかわからない人が増えた。「東の朝炊き、西の昼炊き」と言われたのは遠い昔の話だが・・・ ご飯をいつ炊くか。もちろん今では夕食前に炊くのが一般的だ、ところが細かく見ていくと東西で微妙に違いが見られる。ハウス食品の炊飯のタイミングを全国的に調査したのを見ると、大阪では「昼に炊く家庭」が11’6%で、他の地域に比べて多いことが判った。昼食にお米を食べている割合も全国で50%を超えている唯一の地域である。東京では「昼に炊く家庭」は5’9%で、昼食をパンにしていうる割合が全国で一番多い。ちなみに「朝に炊く家庭」が最も多いのは北海道で、78’9%と群を抜いて割合が高くなっている。
近世の江戸・大阪比較論として知られる「守貞漫稿」には、東西の食生活の違いが具体的に述べられている。それによれば、畿内では江戸時代には商家などでも昼に炊くのが普通だったようだ。朝食は、前日の残りの冷ご飯をお粥にして食べる。ちなみに大阪では「おかいさん」と呼ぶ。おかずは一汁一菜 。昼にご飯を炊き、おかずは煮物または魚にお味噌汁。夕飯は冷ご飯に簡単なおかずという具合だ。対して、江戸では朝は暖かいご飯に納豆と海苔、お味噌汁。昼には冷飯に一菜と魚肉がつき、夕飯は茶漬け飯に香の物というのが一般的。冬には味噌汁に入れて再炊し、雑炊にして食べることもまれにあったらしい。
お粥との明確な区別はないと言われる
粥状に米を煮るとき、有り合わせの魚介菜藻を混ぜ塩、しょうゆ、味噌などで味付けする。
やや回復した、病弱者の栄養補給、冬期の保温食、余った食材の利用など様々な目的で昔から重用した。
個人的な好みとして、カキ、卵、鶏肉、ふぐチリや寄せ鍋などの残り汁に飯を加えて作る雑炊などがある。
貴族の間の本式の食べ方は、「飯(いひ)」(別称「強飯(こわいい)」と呼ばれる、お米を甑(こしき)で蒸したものです。
しかし、日常的には「粥(かゆ)」と呼ばれる釜で煮たものが、主に朝食として用いられていきます。
やがて、次第に「固粥(かたかゆ)」(別称「姫飯(ひめいい)」)と呼ばれるものが好まれるようになっていきます。
(現在私達が食べているごはんは、この「姫飯」にあたります。ごはんからつくった糊を「姫糊」と呼んだり、正月2日を「姫はじめ」と呼んで、釜で炊いたごはんを食べる日としたのは、ここに由来します)
その他の食べ方としては、ご飯を干した「ほしい」や、おにぎりにした「屯食(とんじき)」、「焼米(やきごめ)」などがありました。また、変わった食べ方として、夏は「水漬け」や「水飯(すいはん)」と呼ばれるもの、冬は「湯漬け」なども食べられていました。
何れもお米を常食していたのは貴族のみであり、一般庶民の間では雑穀が主食でした。
いわゆる半つき米で炊いたご飯のことです。もしくは、白米と大麦を半々に混ぜたお米のことを意味します。 近畿地方や中国地方では、明治時代まで半白というのは麦飯の混炊の意味でもありました。 江戸末期までは、徳川将軍家では正月三が日は麦飯を食べていたと言われています。
右 大さじ・・・15cc
中 小さじ・・・5cc
左 計量カップ・・・200cc 200ccって牛乳ビン1本分と同じ量。
「ご飯」の炊き方 炊飯器のない鍋での場合の炊き方
■お米の計り方
お米を計る。
カップで計ってすりきる。
次はお米を洗う。お米についてるぬかを取るため。
はじめはたっぷりの水でサッと洗い流す
最初はお米が水を吸いやすい。
サッと洗い流さないとぬかの入った水を吸収し、ぬかの味がするご飯になる。
最初はサッと洗って、その次から2〜3回研ぐ。
その後は、ざるに上げて,夏なら30分,冬なら1時間くらい置く。
時間がたったらお水を入れる。
お水の量は水につけておいたお米と同じ量にする。
※ここが問題の所・・浸漬しておいたお米は水を吸う。古米と新米では、この水分が違うので、炊きあがりに違いがでる。普通の状態では、生米に対して約2割増しの水の量になるが、水分の多い新米の場合は同量か約1割増し位にする。逆に古米の場合は、生米に対して約2.5割増し位の水の量にする。これを計算してみると、
通常のときは、 米3合に対して、水3.6合
新米の場合は、 米3合に対して、水3合〜3.3合位
古米の場合は、米3合に対して、水3.75合位
すると古米から新米に切り換わるときの目安では、3.3合÷3.75=0.88となるから、新米か古米になるときには、約一割を目安に水を減らすというのが、一般通例で言われている。
お米は炊き上がると2.5倍にふくれる。
だから鍋で炊くときは、お米の量の3倍くらいの容量が必要となります。
1.沸騰するまでがんがん強火
2.沸騰したら弱火で15〜17分間じっくり炊く
3. 火を止める前に、また一気に強火にして10秒数える
その後15分間くらい蒸らします。
特にご飯は、火を止めてからの15分間。
この蒸らしの間はどんなことがあってもフタを開けない
■フタを開けて、底からよ〜くお米をほぐして余分な水分をとばす。
そして鍋に布巾をかけて食べる時までまたフタをする。
釡飯でも炊飯器でもOK、要はなんでも混ぜて炊飯器で炊いちゃう。
やせ土で育った大根に雑穀を混ぜた「糧飯(かてめし)」で空腹を満たした生活のときのイメージが強いが、今でいうと健康食。「釜めしなんて、昔の、釜で炊いたごはんへの郷愁というだけのこと。一人前 ずつの炊飯で、おいしいごはんができるわけないんだし、とても料理と呼ぶには値しないシロモノだよ。ま、ままごと(飯事)と思えば、目クジラたてることもないけど」
「はじめチョロチョロ、なかパッパ」という、ごはんを炊く要領はご存じだろう。「フツフツいったら火を弱め、赤子泣いても蓋とるな」と続く。最初は弱火で釜の中ぜんたいに対流が起こるようにし、次に強火で米を煮沸し、米の中心まで水分が吸い込まれたら、火を弱め蒸しに入る。最後に一呼吸だけ強火をかけて焼きあげる。炊くという調理法は、煮たあとで蒸しと焼きを加えて、水分を飛ばしてしまうのがポントだ。
この微妙な火加減は、最新のマイコン制御の炊飯器でも、まだまだ理想にはほど遠い。ところが、釜めしならそれができる。一人前ずつという、一見不利に見える条件も、釜が小さいからこそ、中の米をいっせいに煮沸できるので、中心部と外側のムラがなく、失敗が少ないことになる。
単なる郷愁というムード的なものでなく、事実、昔の釜炊きと同じ原理を、ミニサイズで再現できるわけだ。
戦時中に流行した糧飯(かてめし)が釜めしの原型とみられるが、人気の具は、カキ、カニ、エビ、貝柱、マツタケ、タケノコ。
昆布ダシに色付け程度にしょう油を加え、炊飯段階が蒸しに入った頃合い、具を一種類だけ載せる。そのまま炊きあげれば、具の香りが全体に染みわたった、ほかほか釜めしの出来上がり。
秋田県には、お米にまつわる料理が数多くありますが、その中で「たんぽもち」と「きりたんぽ」が代表的です。
たんぽもち
粘りの強い新米を炊いてすり鉢でつぶし、杉(柾目)の串につけてちくわ状の形にし、炭火で焼き上げたもの。それを味噌につけて、田楽として食べます。
きりたんぽ
たんぽもちを三切れか四切れにして、鍋ものにしたもの。
鳥肉をだしにして、野菜などを入れて煮込みます。
秋田県内であれば、どこでも賞味できます。
新米のとれる秋から冬にかけてが最盛期。
こんがり焼けた米と醤油の風味の融合が、とても美味です。
◆五平もち
長野県の飯田地方に古くから伝わる郷土の味です。
小判の形につくるので、この名前がついたものと考えられます。
炊きあがったご飯をすり鉢でつぶして、これを割木につけ、両面を焼いたものに、味噌や生姜入りの醤油をつけて食べます。
ご飯を少し固めに炊くことと、ご飯の練り具合が味の決め手で、さらに杉の木の香りが味を引き立てます。
春は木の芽を、秋にはくるみなどで変化をつけています。
長野県以外にも、愛知県三河の鳳来寺山、岐阜県の恵那などで名物となっています。
◆笹団子・ちまき
共に、新潟県名物として知られる、素朴な味です。
笹団子
うるち米で作った草もちの中に、小豆のあんを入れて笹でくるんだものです。
よもぎと笹の香りが特徴です。
今や雪国を代表する銘菓として、全国的に有名です。
ちまき
もち米を笹でくるんだもので、きな粉などをつけて食べます。
もち米に各種の具を入れて調理した炊き込みご飯を笹でくるんだものもあります。
日本人の主食であるごはんを表す言葉には、様々な習慣や伝承、そして日本人独自の考え方がこめられています。
◆よそう
ごはんだけ「盛る」ではなく、「よそう(装う)」と表わします。これは、お米へのありがたさが反映された習慣です。
◆めし(飯)
「召し」。お米が神様に奉納する特別なものであったことから、この言葉が使われたものと思われます。
◆銀シャリ
西南戦争の頃、兵士達がその色から、稗飯(ひえめし)を金、米飯を銀と呼んだのが起源とされています。
シャリは、梵語の舎利・つまり仏様や聖者のお骨のことを指す仏教用語です。
上記のように、お米を尊きものとし、田の神に感謝し、特別な思いを白いごはんに抱いてきた日本人。私達も「装う」心意気を忘れずに、炊きたての銀色に光るごはんを戴きたいものです。